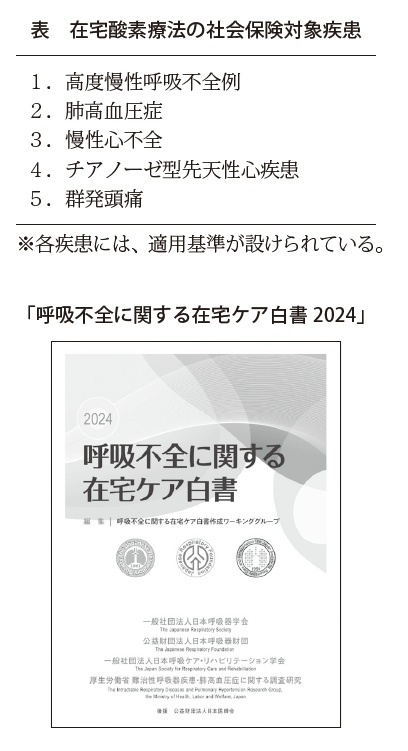齊藤
呼吸不全と在宅呼吸ケアということで、在宅酸素療法についてうかがいます。
まず在宅酸素療法の目的についてお聞かせください。
平井
在宅酸素療法の適応になるのは慢性の呼吸不全の患者さんが多いのですが、治療の目的の一つは呼吸困難といった症状を軽減させてあげること、次に、低酸素血症に伴う疾患の進行や増悪を回避して、予後を伸ばす、また生活の質(QOL)を向上させることになるかと思います。
齊藤
生命予後もこれで延長するのですか。
平井
すべての疾患に対してエビデンスがあるわけではありませんが、例えばCOPDに対して在宅酸素療法を行った患者さんとそうでない患者さんでは、やはり行っている方のほうが生命予後は良かったという報告もあり、生命予後の改善にもつながる治療法の一つだろうと思います。
齊藤
酸素療法が家でできない場合は病院にいるしかないですが、日本で在宅酸素療法ができるようになったのはいつごろからですか。
平井
1985年からこの治療法が保険適用になっています。それまでは、例えば急性疾患で呼吸不全の状態になられて、入院治療を受けて、症状が安定はしたのだけれども低酸素血症が続いてしまい、持続的に酸素吸入が必要であるといった患者さんは、そのまま酸素投与だけのために入院治療を続けざるを得ませんでした。しかし、在宅でも利用可能な酸素濃縮器が開発されるようになって、1985年からは在宅酸素療法が保険適用にもなりました。このように、慢性の呼吸不全患者さんが在宅で酸素療法を受けることができるようになり、治療法として広がっていったというのが歴史的な経緯になるかと思います。
齊藤
保険で認められたことで患者さんの負担が軽減されているということですが、アメリカと比べると、日本の状況は違いがありますか。
平井
米国とは違って、日本は社会保険が適用になっていますので、適用基準が決められてはいるものの、患者さんにとっては、保険診療で治療が受けられることで、負担の軽減につながっているのではないかと思います。
当初1985年時には、慢性呼吸不全の患者さん、あるいはチアノーゼ型の先天性心疾患の患者さんが対象でしたが、その後1996年からは肺高血圧症、2004年から慢性心不全の患者さん等に適用が拡大されて、この治療法も広がっていきました(表参照)。
齊藤
適用は、血液中の酸素濃度で決められていくのですね。
平井
慢性呼吸不全の状態であることが条件になりますので、動脈血の酸素分圧でいうと60Torr以下が必要な条件にはなってきます。
齊藤
患者さんが拡大しているということで「呼吸不全に関する在宅ケア白書2024」がインターネットで発表されていますけれども、実際にどのような疾患の方が日本でこれを利用しているのですか。
平井
在宅酸素療法を受けている多くの患者さんが慢性の呼吸器疾患の患者さんですが、原因疾患の中で最も多いのがCOPD、すなわち、主に喫煙曝露による慢性気管支炎や肺気腫といった病態です。それから、間質性肺炎、肺結核後遺症などといったものが主な疾患になります。
その中で今回の「在宅ケア白書」で明らかになったのは、以前と比べ、相対的にCOPDの割合が減り、むしろ間質性肺炎の割合が大きく増加してきているところが特徴になっています。
齊藤
その他、肺癌の患者さんなどもある程度いらっしゃるのですか。
平井
はい。そのほかの肺疾患としては、悪性疾患の患者さんや塵肺の患者さんなどが含まれます。
齊藤
さて、酸素を与えるにも、処方があるのですね。
平井
例えば在宅酸素療法が適用となる患者さんがおられて、治療を開始するとなった場合、医師は、何リットルの酸素が必要か、安静時、労作時、労作後や夜間睡眠時などそれぞれどれぐらいの酸素量に設定するか、また、どのような機器を使うかといった内容を検討し処方するという具合になります。
齊藤
酸素を供給する機械にも種類があるのですね。
平井
在宅での酸素療法を行う方法として大きくは2つあります。一つは酸素濃縮器、もう一つが液化酸素です。ただ、大半は酸素濃縮器を使っている患者さんになります。
これは小型の冷蔵庫ぐらいの大きさのものを自宅に置いていただいて、空気中の酸素を濃縮して患者さんに吸入してもらうもので、電源があれば連続使用できます。メンテナンスも比較的容易であることから、広く使われています。
一方で、停電になったときには当然、機械としては働きませんので、問題になること、また空気中の酸素を濃縮するので、流量が多くなると吸気中の酸素濃度が低下してしまうという欠点もあります。
齊藤
これは業者からのリースで行っていくのですね。
平井
はい。酸素濃縮器、液化酸素、いずれにしても、医師が処方したら、通常は医療機関と酸素事業者との間でレンタル契約をしておいて、その事業者が患者さん宅に処方に応じて機器を配送、設置してくれます。患者さんは月1回程度受診をして、医師は指導管理をすることで治療を継続していく、そのような流れになります。
齊藤
日本では災害対応が重要になりますね。
平井
ご指摘のとおりで、今般の能登半島の災害、阪神淡路大震災や、東日本大震災の場合もそうでしたけれども、災害時に停電になると酸素濃縮器を使った在宅酸素療法を受けている患者さんは酸素ボンベに頼るしかなくなります。酸素が必要な患者さんが酸素療法を継続できるよう、いかに迅速に対応できるかというところに、各事業者それぞれ取り組まれています。
齊藤
さらに、介護するご家族の貢献も非常に重要でしょうね。
平井
ご指摘のとおりで、呼吸器疾患に限らず、日本の場合、高齢化とともに慢性呼吸不全の患者さんを支える介護者の負担も考える必要があると思います。
どうしても患者さん自身は酸素を吸いながらになりますので、様々な日常生活の活動が思うようにいかない。多くはご家族になろうかと思いますが、介護者をいかに支援していくか。したがってご家族の負担だけではなくて、地域で支え合うような取り組みが望まれるのではないかと思います。
齊藤
非常に発展してきたということですね。
平井
在宅酸素療法を主にお話ししてきましたが、特に患者さんを取り巻く管理という点では、酸素療法や薬物療法だけではなく、栄養管理や運動療法も慢性の呼吸器疾患の患者さんにとって、非常に重要な要素になってきます。そのためには医師だけではなく、看護師や薬剤師、理学療法士、あるいは栄養士、地域の方々も含めてチーム医療で取り組んでいく必要がある領域かと思います。
齊藤
ありがとうございました。